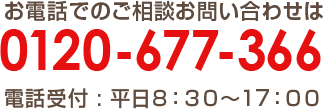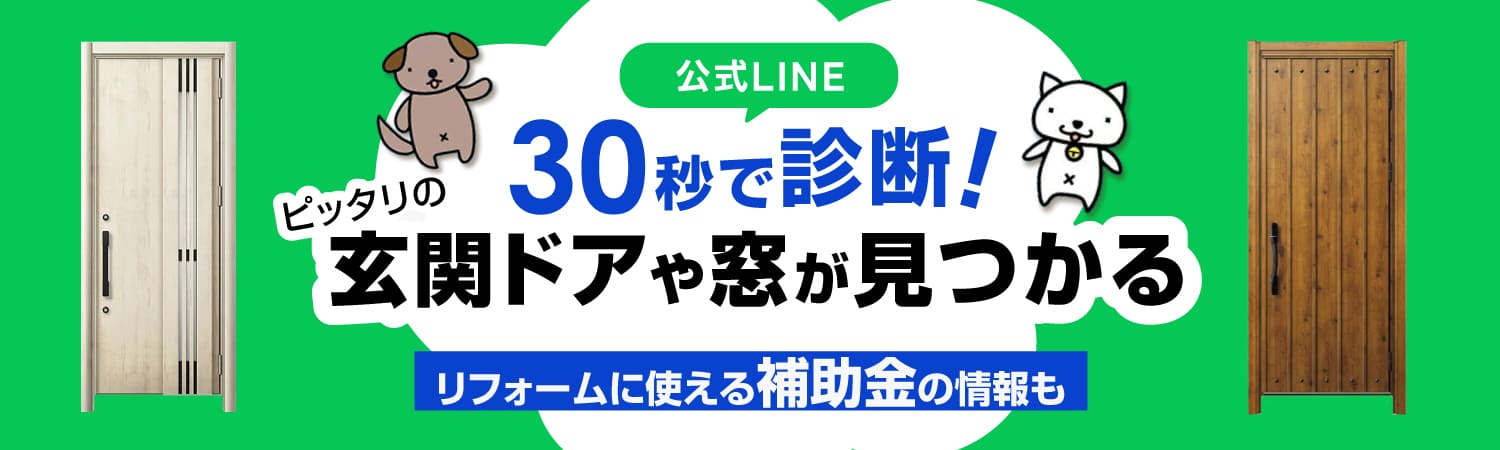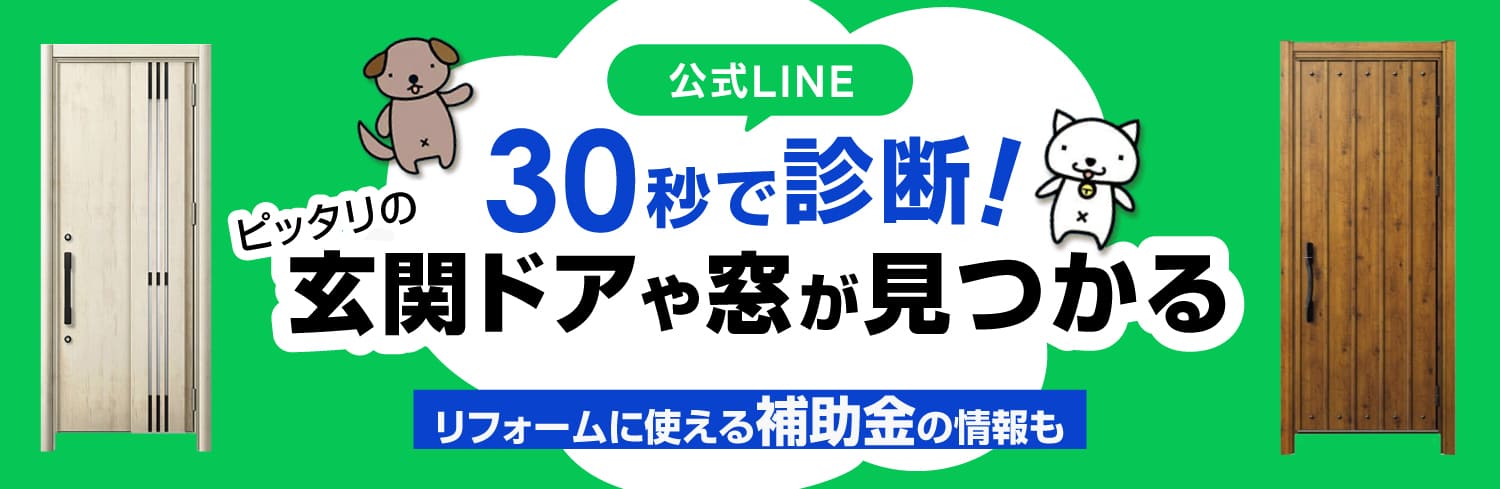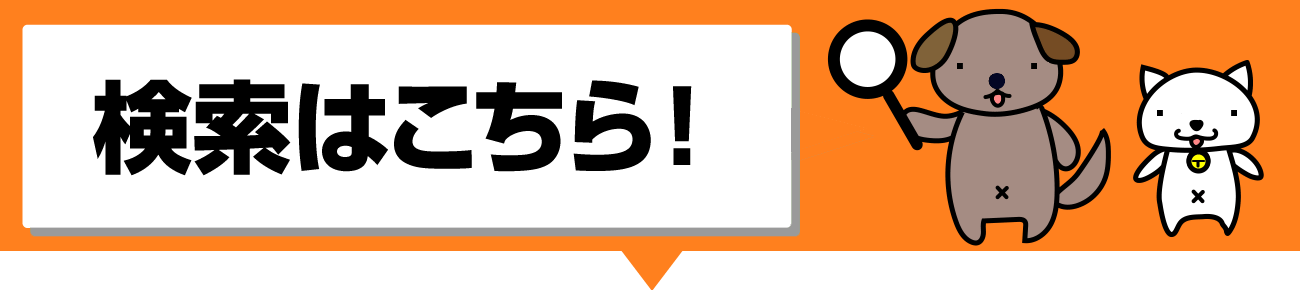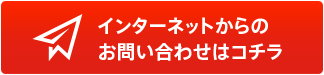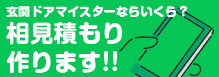玄関には上り框という段差があります。この段差によって靴を履き替えたり室内の清潔感を保っていたので便利な役割を果たしていました。しかしこの段差は厄介な点もあるためバリアフリー対策を施す上では必要無いと考えられてもいます。そこで今回は玄関の段差がもたらす役割とバリアフリーとの関係性についてご紹介します。
玄関の段差(上り框)について

日本の住宅には玄関に上り框(あがりかまち)と呼ばれる段差があります。上り框とは土間と床を隔てる段差の先端にある横木のことです。日本には昔から室内へ入る際に土間で靴を脱いで室内へ上がる習慣がありました。現在の日本の住宅は大半が洋風住宅になっていますが、上り框の習慣は今の住宅にも引き継がれています。
上り框は日本の風習
昔は玄関の上り框を利用して人とのコミュニケーションを図っていました。近隣の住民や突然の訪問者と世間話をする際は中に上がるという手間をかけずに、お客には上り框に座ってもらってその場で話をしていました。この状態で住人が座るとお互いの目線が同じ高さになるので対等な立場で会話することが出来ました。
他にも外出時あるいは帰宅時に靴を脱ぎ着するために一旦座る場所として使用したり、帰宅後の荷物置く場所として活用することも出来ます。このように上り框は様々な活用方法で昔から親しまれていました。
玄関の段差は必要?

玄関の上り框は日本の住宅ならではの風習なので、昔から当然の如く玄関には段差が付けられていました。玄関の段差は見た目だけでなく機能的な役割も果たしていますが、人によっては段差があること不便に感じることもあります。
玄関の段差のメリット:掃除が楽
玄関に段差が付いていると玄関の掃除がとても楽になります。玄関は靴を履いた状態で出入りする場所なので靴の裏の泥汚れが入り込んでしまいます。そして靴を脱ぎ着する際に靴裏に付いた泥汚れが落ちて玄関に溜まってしまうことがあります。玄関に段差が付けられていれば泥汚れが土間に溜まるので、家の中まで入ることは防いでくれます。
そのため玄関に汚れが溜まっても土間だけ掃除すれば清潔感を保てます。雨が降った際も同様で、靴裏に溜まった雨水が土間で止まってくれます。また泥汚れは靴裏だけでなく玄関ドアを開けた瞬間に入って来ることもありますが、段差によってゴミやホコリが中まで入って来ることを防いでくれます。
玄関の段差のメリット:物が置ける
玄関に段差があると上り框から先は土足で入らない場所なので清潔感が保たれています。そのため玄関に置物・観葉植物・靴箱など色々な物が置けるようになります。物を置いてデザイン性を追求すれば玄関がより一層おしゃれな空間になります。
玄関の段差のメリット:気持ちの問題
玄関の段差は日本の住宅に昔から存在していた文化です。日本の住宅の在り方が体に馴染んでいる人にとっては玄関で靴を脱いで段差を上るという行為は当たり前のように思っています。逆に欧米の住宅では家の中でも靴を履いたまま出入りするので玄関に段差はありません。
日本の住宅でもこの欧米のスタイルを取り入れた家は存在しますが、段差を上がらず靴のまま玄関を通ると帰宅した実感が湧かないという意見を聞きます。今まで当たり前のように行っていた「靴を脱いで段差を上る」という行為をしないと、帰宅しても気持ちが入れ替わらないのだそうです。これは気の持ちようですが、日本の風習に馴染み切っている人の中にはそういう方もいらっしゃいます。
玄関の段差のデメリット
日本の住宅らしさの象徴であり機能的な役割も果たす玄関の段差ですが、考え方によってはデメリットになる場合もあります。それは障害者や足腰が弱っている方にとっては玄関の段差を上ることが体力的に難しいという点です。私達が普段何気なく行っている行為も体に不自由を抱えている人にとっては困難である動作は日常生活の中で多々あります。
その中でも段差を上がるという行為は非常に難しい行為であると考えられます。足腰が弱っていて杖を突きながら歩いている人は自分の足だけで段差を越えることは非常に厳しいですし、松葉杖や車椅子を使って移動する方にとっては段差を上るという行為は不可能です。そのような行為を外出・帰宅の度に毎回行うというのは精神的ストレスにも繋がります。
段差の高さによる違い
玄関の上り框の段差はそれぞれの住宅によって異なります。上り框の高さは特に決まっているわけではないので新築住宅を設計する際にアレンジ出来ます。そのため数cm程度しかない段差もあれば、30cm前後の階段よりも高い段差を付けた上り框まで種類は様々です。
段差の高さによって上り框の性能が変わります。高い段差を付けた上り框はしっかりと段差を越えたという実感が湧くので上り框としての存在感を発揮出来ます。また段差が高い分泥汚れが中に入る可能性も低いので掃除がとても楽になります。
逆に数cm程度の低い段差を付けた場合、昇り降りにかかる体の負担が少ないのでバリアフリー対策に向いています。また段差が低いと上り框と土間の間にギャップが生まれないので玄関全体に一体感をもたらすことが出来ます。
上り框の段差は高い方と低い方のどちらが良いかは人それぞれの考え方次第です。しかし現在の住宅事情はバリアフリー対策を導入する傾向にあるので上り框の段差は低めあるいは無くす方向が強まっています。
段差を無くしてバリアフリー対策を施す

現在の住宅は高齢者や障害者でも不自由なく利用できるようなバリアフリー化を積極的に進めています。玄関に関しては段差を無くすことでバリアフリー化を促しています。
玄関に段差があると車椅子や松葉杖を使用している方、あるいは足に不自由がある人にとっては移動しづらくなってしまいます。そのため現在の住宅の段差は昔に比べて低くなっています。バリアフリー住宅の基準では18cm以下の段差が望まれており、医療・介護施設では玄関の段差を無くしてスロープを付けていることも多く見られます。
自宅のバリアフリー対策
自宅に本格的なバリアフリー対策を施すのであればリフォーム工事が必要になります。しかしリフォーム工事は高い費用がかかりますし、工事中は第3者が出入りすることになるので非常に不便です。しかしリフォーム工事を行わなくても バリアフリーグッズを取り入れることでバリアフリー対策を施すことが出来ます。
簡単なバリアフリーグッズの一つとしてステップがあります。玄関に設置するステップは式台と呼ばれており、上り框より少し低い段差になっています。式台を使うことによって低い段差を上ることになるので、上り框による足の負担を緩和出来ます。
玄関の土間にベンチ・椅子を置くこともバリアフリー対策に繋がります。土間にあるベンチ・椅子に腰掛けて靴を脱ぎ着すれば動作が少なくなるので、外出・帰宅時の動きがスムーズになります。
玄関に手すりを付けることもバリアフリー対策として有効です。足腰が弱っている方にとっては段差を上るという行為は非常に困難なので、手すりを利用して体の負担を減らせば上り框を上ることが楽になります。
ステップや手すりなどのバリアフリーグッズは各店舗で販売されているので後付けも可能です。もし自宅に高齢者や障害者がいる場合、それぞれの住宅事情を考慮して玄関の段差の在り方を考えてみましょう。
まとめ
今回ご紹介した内容は以下の通りです。
・玄関の上り框は日本古来の風習
・段差があると掃除が楽になるが段差を上るという行為は体に負担のかかる事でもある
・バリアフリー化を考えているならば上り框の負担を減らすような対策が必要
玄関ドアマイスターの見積フォームへのリンク
https://nakamura-genkan.com/item-search/